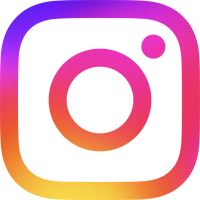【コラム】続・子どもの勉強を見られない時はどうすればいい?
2025年4月23日
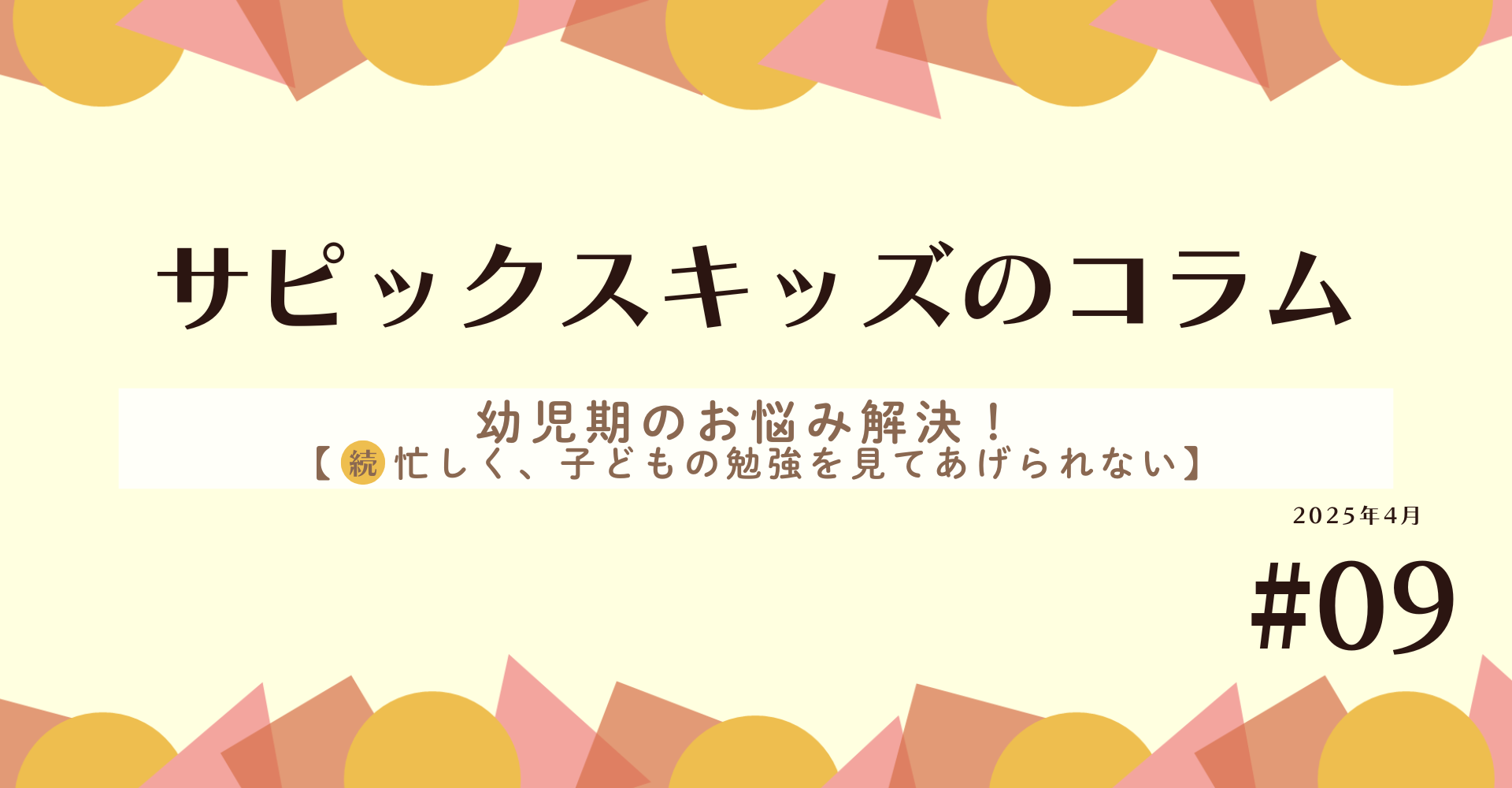
▷ 家でできることで、おすすめはありますか?
昨今の中学入試問題でも、机上の学習のみだと太刀打ちできないものが多くあります。
何より、テキストやペーパーの学習の理解度を高めるためには実体験が大切だと痛感します。
楽しんで取り組めることは、お子様お一人おひとり、みんな違います。
前回のお悩みに引き続き、ご家庭で具体的にはどのようなことをしたら良いのか。
短時間で毎日できることの具体例を、考えてみました。
ポイントは、「お子様も、保護者の方も楽しめる」ことです。
生活の中での経験、体験を通して学ぶことが、何より重要であると考えています。
◆お手伝い
今回は、料理・食事・後片付けを例に挙げてみます。
野菜を洗うお願いをすると、土がついていればどこで大きくなったかを考えるきっかけにもなります。
包丁で切った後の切り口を見せてみると中がどのようになっているか、種があるかないか、食べられる部分がどこなのかを知ることができます。
加えて、食事中に豚汁に浮いた円い形を見て、何かを考えてみるのも学びです。
お皿を洗う時にはぬるぬるしているな・・・水に油は浮いていると気づくことができますね。
また、一緒に献立を考えてもらうのもひとつの方法です。
お買い物をするときにも、考えた献立に入っている野菜等を一緒に探すことで、食べ物の旬を知ることができます。
そのうえ、陳列されている棚を見て「とりやすく低いところに子どもたち向けのお菓子が並んでいるな」など発見をするのも楽しいですね。
◆工作
一緒にお子様のわくわくするものをつくってみるのはいかがでしょうか。
十分に、図形の学びに繋がります。
例えば、簡単にパズルをつくることもできます。
折り紙に好きな絵や字を書いて、難易度に応じて3~5つのパーツにわけます。
ハサミを入れる数が多いほど、難しくなります。
できたら、一緒につくってみてください。
どちらがはやく完成できるか、などルールを設けるのも一つです。
ほかにも、「箱を分解して、一枚の紙にしてみよう」と切り開くだけでも、気づきがあります。
◆ひらがなの読み書き
小学校入学前にどこまでできていたら良いかの目安について「何もしなくてもいい」と言われつつも、本当に大丈夫なのか心配になってしまうかもしれません。
ひらがなの読み書きについては、「書ける!」と思うことで自信をもって学習をスタートできる部分もあるかと思います。
「毎日続けて、しりとりをしてみよう。今日は『あ』から始まる言葉を1つノートに書こうね。明日はその続きの言葉にしようね。何個連続で書けるかな?」
保護者の方と交互にしても、面白いかも知れません。
「今日は●●ちゃんの読みたい本を一緒に読もうか。続きは明日ね。」
「くまちゃん役になって、台詞を読んでもらいたいな。」
など、お子様に読んでもらうことも、1年生に近くなったらぜひ行ってみてください。
お手紙交換をして、積極的に文字を書くようになったお子様も多いです。
保護者の方から返事をもらうことを楽しみにしているお子様もいらっしゃいました。
保護者の方のお時間、状況もご家庭によって様々です。
だからこそ、保護者の方も一緒に行いたくなるような、日々の楽しみのひとつになるものをご提案できればと考えてみました。
焦らなくて、大丈夫です。
お子様にとって、
「大好きなものに夢中になって、存分にやり尽くす時間である」
「普段できない挑戦をたくさんすることができる時期である」ことを、心から願っております。
一緒に、よりお子様に合う楽しみ方を探してみませんか?
\\ こちらもおすすめです //
タングラム・ハートの詳細はこちら
わくわくきらめき脳の詳細はこちら
現在、東京都に3校舎(代々木・豊洲・お茶の水)展開しています。
対象学年は年中生・年長生で、秋頃から新年中生の募集を開始します。
各種情報を発信しています。ぜひご覧ください!