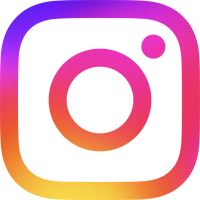【コラム】集中力を高める方法
2025年8月27日
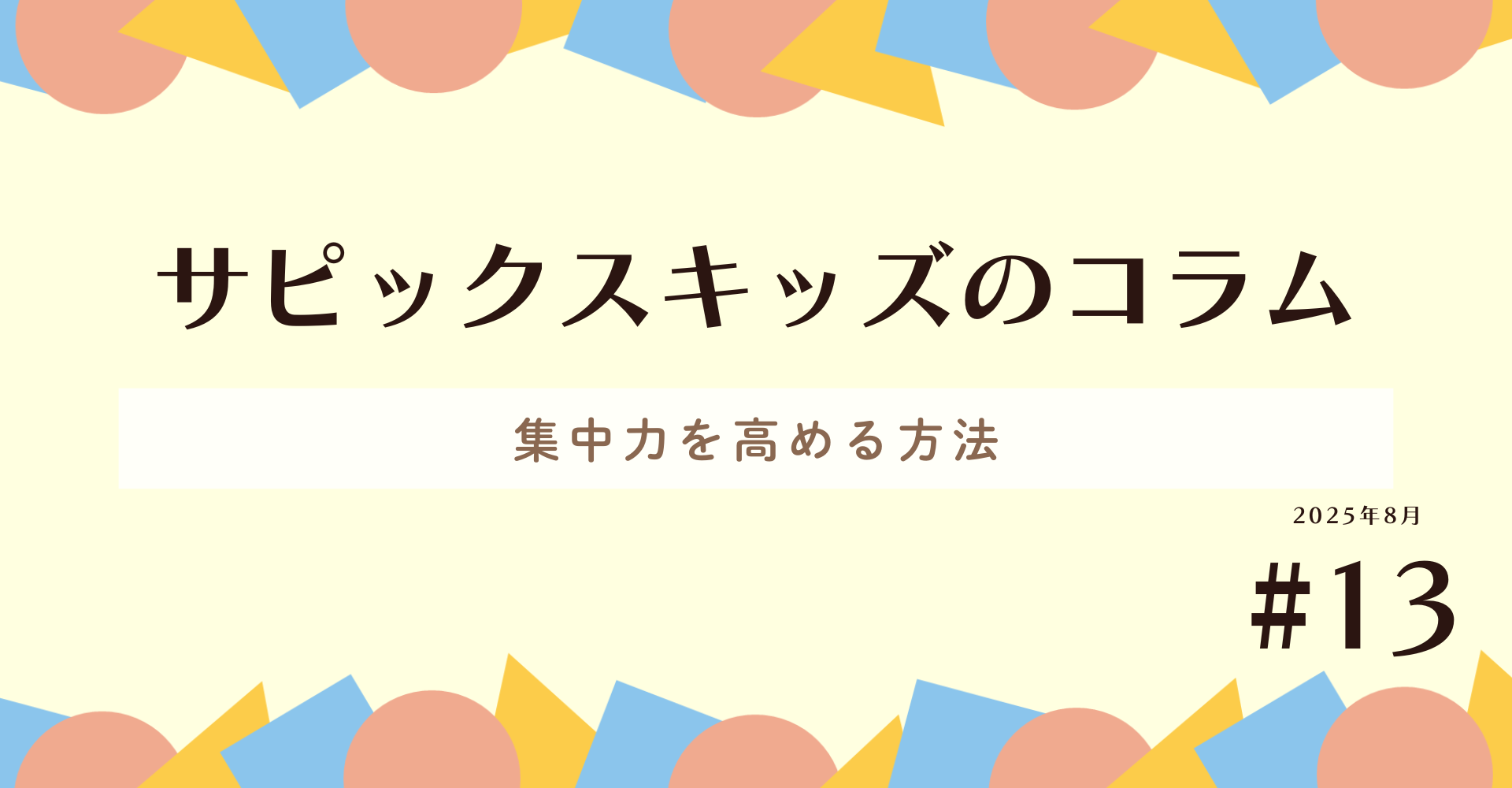
▷ 気が散ってしまい、宿題が進みません。
小学生までのお子様に「机に向かう」よう促すのは、大変なことだと思います。
コラム03(2024.10)【学習習慣をどうやってつけるの?】でも触れましたが、
子どもたちの集中力が続くのは、幼児期では「年齢+1分」、大人でも15分程度だと言われています。
お子様向けの教育番組の多くが約15分で終わるのも、そのためです。
SAPIX kidsの平常授業は各学年90分です。
体験授業にいらっしゃる方からは、「90分も持つか心配」とよく伺いますが、実際にお子様の姿をご覧になって
「最後までしっかりと座って授業に参加できている姿を見て驚きました」と感激されることも多くあります。
授業中には、子どもたちからも「もう終わり?!」「もっとやりたかった」という声が上がり、
授業が終わっても「まだ帰りたくない!」とニコニコしているお子様もお見受けします。
これは、90分間ずっと座って話を聞くのではなく、
手や身体を動かしたり、考えたり発言したりしながら子どもたち主体で授業が進むからです。
お子様自身が主人公となること、自らが体験し発見ができること、達成感を味わえること、
何より「楽しい」と感じることが、学びのモチベーションに繋がっていると実感します。
今回は、集中力を育てるため授業で行っている工夫やご家庭でできることをご紹介します。
読み聞かせ
子どもたちは、読み聞かせが大好きです。保護者の声で、対話をしながら同じ本を読み、
その物語の世界観に没入する体験や、主人公と同じ気持ちになる経験は生きた学びになります。
2~3分だけでも構いません。図鑑でも構いません。
ぜひお子様の好きな本を一緒に読んでみてください。
時間を計る
ゲームの要素をちょっと取り入れることもお勧めです。
最初はドキドキしていた子どもたちも、「ようい、ドン!」の掛け声とともにストップウォッチを使うと、
静かに取り組みます。
5分は意外と短いようで長いもの。
しかし、アラームが鳴ると「もう終わり?」とみんな驚いています。
お子様のワクワクする設定をつくる
もしも電車が好きなお子様であれば、机に向かう時間に電車内のような配列でいす等を準備し、
「まもなく発車します」の掛け声とともにスタートをしてみましょう。
長距離列車のボックスタイプの座席のイメージも良いですね。
もしもプリンセスが好きなお子様であれば、お姫様のお勉強時間という設定で、
机の上もきれいにして、お花も飾って・・・と、ごっこ遊びの延長で一緒に楽しんでみるのはいかがでしょうか。
わかりやすいゴールの提示
「今日はこの1問だけ」など、お子様にとってわかりやすいゴールを設定してあげてください。
特に小学生以降のお子様方が「やりたくないな」と思ってしまう理由は、漢字や計算などでたくさんの量をこなすこと、
内容が難しくてわからないことなど、つまらない、やりたくないと感じやすくなるためです。
基礎的な学びは1日1ページなどわかりやすい区切りで、内容の理解が必要なものは欲張らず、
一つひとつ解決していくことが強固な土台作りに繋がります。
今だからこそ、一緒に遊びながら興味関心を深めていけたらと願っています。
お困りになることがありましたら、いつでもご相談ください。
こぐま会の協力のもと、SAPIXのノウハウを生かし「考える力」「表現する力」を養う小学校受験を目的としないSAPIXの幼児教室です。
現在、東京都に3校舎(代々木・豊洲・お茶の水)展開。
年中生・年長生コースのほか、年少生対象の講座も実施しています♪
各種情報を発信しています。ぜひご覧ください!