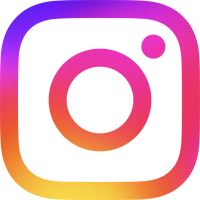【コラム】幼児期の家庭学習~「学ばせる」ではなく「学びに出会う」時間を~
2025年10月29日
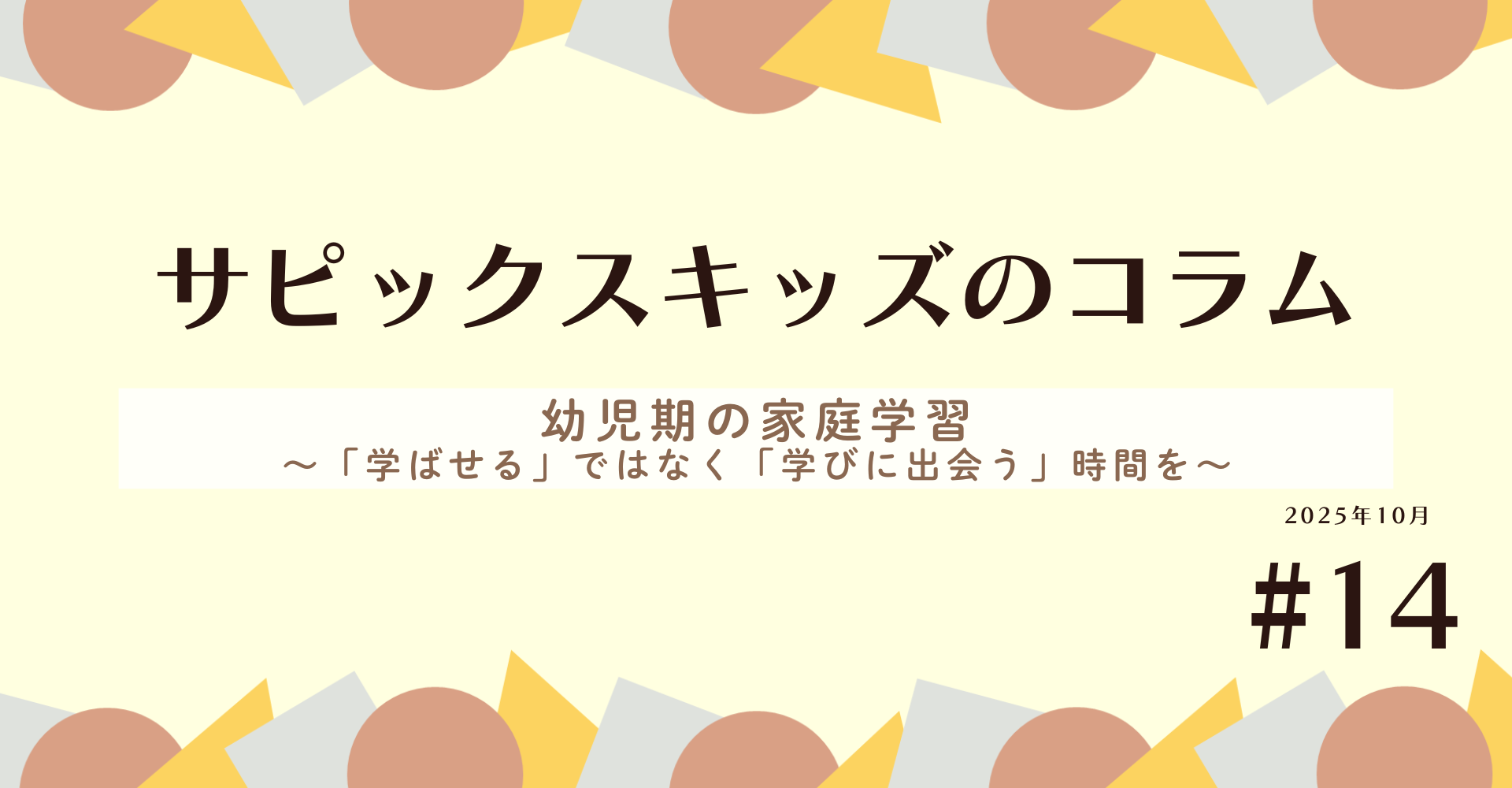
▷ 集中して学べる環境をつくるにはどうすれば良いですか?
保護者の方からよくいただくご相談です。
就学前の学びは、お子様の成長段階に大きな個人差がありますので、家庭によって大きく異なります。
そのため不安に感じられる方も多いかもしれません。
幼児期の学びの意味とは?
お子様はやがて大人になり、自分の力で生きていくようになります。その過程で大切なのは、「自分で考える習慣」です。
与えられた正解だけを追うのではなく、疑問を持ち、「どうしてだろう?」「こうしてみたらどうなるかな?」と試行錯誤できることが、将来につながる学びになります。
幼児期に学びを詰め込み型にしてしまうと、「とにかく正解を言えばいい」という反射的な学習になりがちです。
反対に、考えることに慣れている子どもは、疑問を持ち、調べたり、聞いてみたりしながら、自分なりの方法で解決しようとします。その姿勢こそが、学ぶ力の土台になります。
家庭でできる「学びに触れる時間」の例
◎図形や空間感覚を育てる遊び
段ボールや紙で形をつくったり、三角形などのパズルで分割の感覚を遊びの中で感じ取ったりすることが図形に対する感覚を育てます。さらに、ブロックなどで立体を作ると空間感覚が広がります。
◎話す・伝える経験を増やす
「説明する」ことは立派な学習です。自分なりの言葉で話す機会を増やしてみましょう。
「どうやって作ったの?」「この形は何に見える?」などの問いかけも効果的です。
◎人とのやりとりから学ぶ
同年代だけでなく、年上・年下の子、家族以外の人との交流も大切な学びの時間です。
言葉のキャッチボールや、考えの違いに気づくきっかけになります。
年齢ごとの発達の目安と関わり方
【4歳】― 協力する心が芽生える時期
お友達や家族以外の人と関わる機会を増やし、「一緒につくる」経験を意識してみましょう。
【5歳】― 机に向かう時間が自然と増える時期
文字や数字に興味が出てくる頃です。短い時間でよいので、「書く」「読む」を生活の中に取り入れてみましょう。
図書館や本屋で「自分の好きな本を探す」体験もおすすめです。
【6歳】― 考えを言葉にできるようになる時期
「自分はこう思うけれど、相手はどうだろう?」と視点を切り替える力が育ってきます。
家族でひとつのテーマを話し合ったり、積み木をいろいろな方向から見てスケッチしたりする活動が効果的です。
サピックスキッズでの取り組み
サピックスキッズでは、発達段階に合わせた学びの環境づくりを行っています。
◎ぷれきっず(年少)
親子で参加しながら、木のブロックやごっこ遊びを通して形や数に触れ、学びの場に慣れていきます。
◎年中クラス
大きな積み木でお城を作ったり、具体物を使った「お買い物ごっこ」で数の感覚を育てたりします。
クラス全体でひとつのものを作り上げる中で、友達の意見を聞いたり、まとめたりする力も育ちます。
◎年長クラス
やかんや人形などの身近なものを四方から観察し、見え方の違いを考える活動を行います。
天秤やシーソーなど、小学部につながる学びも、具体物を使って楽しく体験します。
このように、幼児期の学びは「問題を解く」だけではなく、見て、触って、考える経験を通して深まっていきます。
「集中できる環境」は興味から生まれる
子どもは、好きなことには驚くほど集中します。
だからこそ、「何が好きかな?」と観察することが第一歩です。
▷電車が好き
・・・電車の名前を調べたり、図鑑などでその電車を探してみたりするのもいいですね。
▷ブロックが好き
・・・ブロックを形や大きさで分けたり、積み重ねたりすることで数や立体の学びにつながります。
▷料理に興味がある
・・・野菜や果物を包丁で切ったときの断面を観察すると形の学びにつながります。
このように、興味の入り口が学びのスイッチになります。
おわりに ―「教える」ではなく「発見を一緒に楽しむ」
幼児期の学びは、詰め込むことではなく、「学びって面白いね」と感じられる時間を重ねることです。
お子様の興味の芽を見つけ、それを少しだけ広げてあげる―――その積み重ねが、やがて大きな学びの力として花開いていきます。
こぐま会の協力のもと、SAPIXのノウハウを生かし「考える力」「表現する力」を養う小学校受験を目的としないSAPIXの幼児教室です。
現在、東京都に3校舎(代々木・豊洲・お茶の水)展開。
年中生・年長生コースのほか、年少生対象の講座も実施しています♪
各種情報を発信しています。ぜひご覧ください!