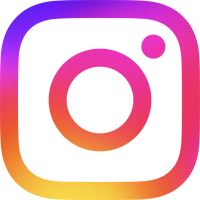【コラム】読解力を育むために~幼児期にできること~
2025年11月26日
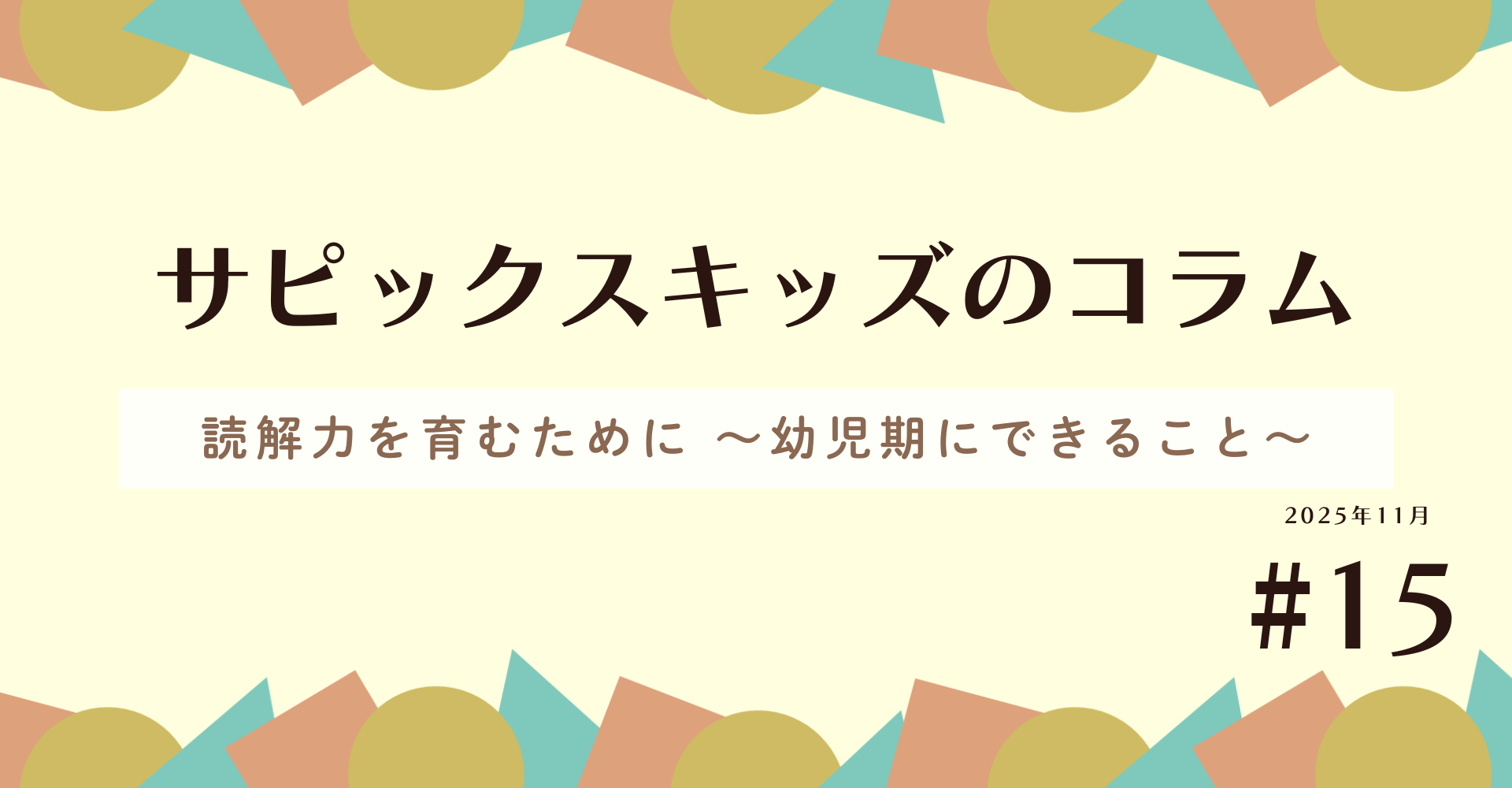
「国語力はすべての学びの基礎」とよく言われます。
では、国語力、特に読解力を伸ばすためには、幼児期からどのようなことができるのでしょうか。
確かに「国語力」「読解力」といった言葉は抽象的で、具体的な関わり方がわからないと感じる方も多いかもしれません。
読解力とは?
読解力とは、ただ文章の内容を追う力だけを指すのではありません。
背景にある時代や社会の状況、登場人物の気持ち、筆者が伝えたかった意図に思いを巡らせる力も含まれます。
「書かれていることをなぞる」だけではなく「なぜ、そう書いたのか」を考えることも、読解力の大切なことと考えられます。
中学受験では、子どもたちの日常とは離れた時代や環境が舞台になっている物語や、聞き慣れないテーマの説明文などが出題されることも多いです。
このような文章を読むとき、理解を支えるのは語彙力だけではなく、背景となる時代の知識や教養、想像力です。
幼児期からできること
◎本に親しむ時間をつくる
動画や音声は受け身でも楽しめますが、読書は自分で言葉を追い、頭の中で世界を描く能動的な行為です。
小学校低学年までは読み聞かせで構いません。
「本って楽しいな」と感じられる時間を一緒に過ごすことから始めてみてください。
本の中で出会う新しい言葉や知らない世界は、子どもにとって小さな発見の連続です。
その積み重ねが語彙力や教養につながり、物語の型や善悪の感覚も自然に身についていきます。
心が動いた読書体験は、子どもの内面を豊かに育ててくれます。
◎本の感想を聞いてみる
「今日、こんな本を読んだよ」と子どもが話してくれたときは、「どんなお話だった?」「どこが面白かったの?」と、ぜひ言葉を返してみてください。一度心に取り込んだものを誰かに伝えることで、理解は深まります。
楽しかった体験を保護者と共有できることは、子どもにとって大きな喜びにもなります。
◎日常で使う言葉を大切にする
家庭で交わされる言葉は、読解の土台になります。
日常会話の中で、できるだけ正しい日本語に触れられるよう意識してみてください。
最近では「ら抜き言葉」などが当たり前のように使われていますが、本来の表現を知ることで、文章を正確に読み取る力につながります。
少し難しい言葉もあえて使ってみると、「それどういう意味?」と子どもが関心を向けるきっかけにもなります。
新しく出会った言葉を自分の言葉として取り込むたび、語彙は自然と増えていきます。
おわりに
国語力はあらゆる学びの基礎であると同時に、物事を考えたり人と理解し合ったりするための根っこにもなる力です。
特別なトレーニングが必要なわけではなく、日常の中にある小さな習慣が、その育ちを支えてくれます。
幼児期から「言葉と出会う時間」を少しずつ重ねていけるとよいですね。
こぐま会の協力のもと、SAPIXのノウハウを生かし「考える力」「表現する力」を養う小学校受験を目的としないSAPIXの幼児教室です。
現在、東京都に3校舎(代々木・豊洲・お茶の水)展開。
年中生・年長生コースのほか、年少生対象の講座も実施しています♪
各種情報を発信しています。ぜひご覧ください!