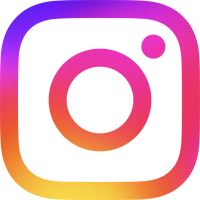【コラム】非認知能力とサピックスキッズ
2025年7月5日
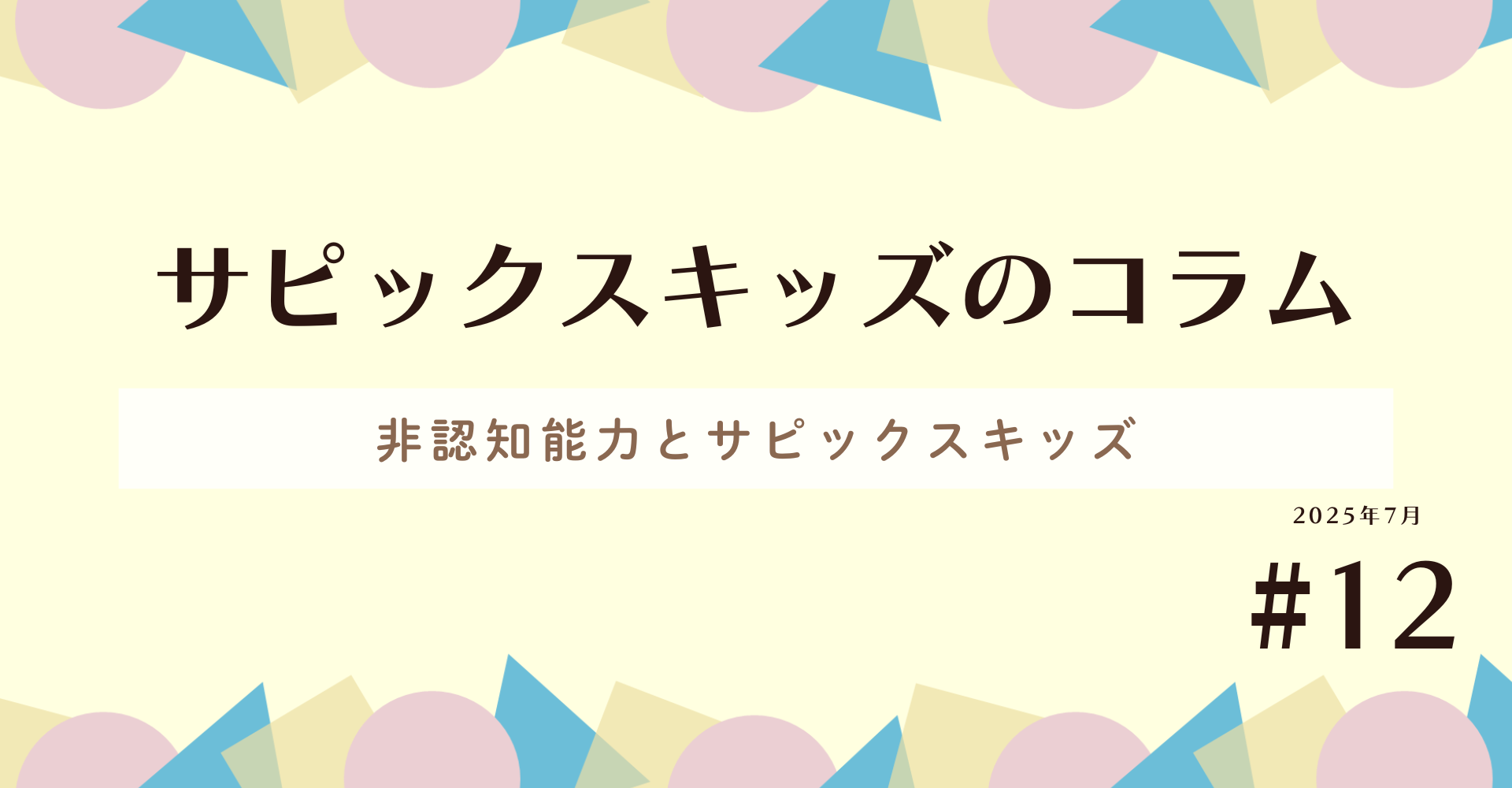
▷ サピックスキッズでは、非認知能力を伸ばすためにどのようなことをしていますか?
非認知能力とは?
IQや学力など数値化できる能力を「認知能力(cognitive skills)」、
一方で数値化できない人間の内面的な力を「非認知能力(non-cognitive skills)」と言います。
非認知能力が注目され始めたのは比較的最近ですが、実は新しく発見された能力でも特別な能力でもありません。
意欲・主体性・好奇心・自己肯定感といった内面的な心の力や、
社会性・協調性・共感力・思いやりなどの他者と関わる力を指しています。
このような非認知能力は、特に幼児期に発達すると言われています。
非認知能力を伸ばすには?
非認知能力は、周囲との関わりの中で自然に身に付いていくものです。
特別なことをしなくても、自然と触れ合ったり、夢中になって遊んだり、
親子で料理に取り組んだりと日常生活で様々な体験をすることで育まれていきます。
また、その発達には、大切にされた経験や愛された経験が不可欠だと言われています。
サピックスキッズでの学びと非認知能力
それでは、サピックスキッズではどのように非認知能力を育んでいるのでしょうか。
サピックスキッズの授業は、以下の三段階で成り立っています。
「身体を使った集団活動」
「具体物を使った個別活動」
「学んだことを確認するペーパートレーニング」
これらすべてにおいて、講師は決して正解を教え込むことはしません。
お子様の柔軟な発想を大切にしつつ、試行錯誤し自分で答えを見つけられるよう寄り添い、
ときに励ましながらサポートしています。
正解することそのものよりも、試行錯誤した過程や懸命に考えたこと、自分なりの意見を持てたことを大切にしています。
お子様の意見に耳を傾けるだけでなく、なぜそのように考えたのかを尋ねたり、
他の考え方ができるかを他のお子様にも質問したりしながら、お子様の思考力を深めていきます。
こうした進め方は、一見遠回りに思えるかもしれません。
しかし、自ら正解にたどりついたという経験は、自信や自己肯定感を育み、
課題に主体的に取り組む意欲や積極性につながります。
また、試行錯誤を重ねること、他のお子様の意見を聞くことで、
正解に至る過程はひとつではなく、さまざまであることが実感できます。
簡単に諦めない力は、このような経験の積み重ねによって育まれていきます。
このような学びを続けてきたお子様は、困難に直面してもすぐに諦めるのではなく、
今ある力でなんとか解決しようとするようになるはずです。
こうして育まれてきた非認知能力は、将来的には中学受験のみならず、
その後の人生を切り拓く大きな武器となることでしょう。
私たちはお子様の豊かな感性に常にわくわくしながら授業を行い、過ごしています。
お子様の好奇心や柔軟な発想を大切にしながら、お子様自身がたくさんのことを吸収し、
より豊かな人生を歩めるよう、サピックスキッズはお手伝いしていきます。
現在、東京都に3校舎(代々木・豊洲・お茶の水)展開しています。
対象学年は年中生・年長生で、秋頃から新年中生の募集を開始します。
各種情報を発信しています。ぜひご覧ください!